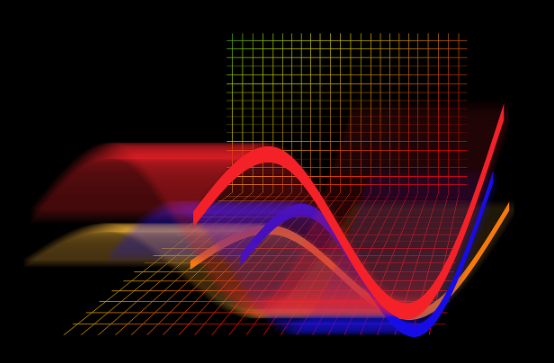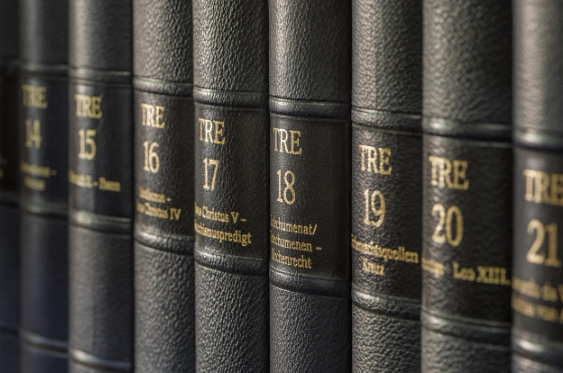
「読解って、結局センスじゃない?」
そんなふうに思っていた時期が、私にはありました。英語の長文を前にすると、目が滑る。単語はわからない、文構造は複雑、設問の意図もつかめない。TOEFLのリーディングセクションは、まさに“苦行”でした。
でも、今振り返ると、読解力こそがTOEFL攻略の鍵だったと思います。今回は、私がTOEFL ITP 400点台から大学院合格(ITP 550点)に至るまで、読解力をどう鍛え、どうスコアアップにつなげたかを、実体験を交えてお話しします。
◇「読めない」から始まったTOEFLの壁
TOEFLのリーディングセクションは、アカデミックな文章が中心。生物学、歴史、地質学、芸術論など、専門的なトピックが並びます。英語力以前に、内容が難しい。しかも制限時間内に複数の文章を読み、設問に答えなければならない。
私が最初に受けたTOEFLでは、読解セクションの正答率は半分以下。設問の意味すらわからず、選択肢を「なんとなく」で選んでいたのが現実でした。
◇読解力は「単語力」×「構文理解」×「量」
読解力を鍛えるには、いくつかの要素があります。私が特に意識したのは以下の3つ:
- 単語力の強化
読めない原因の多くは、単語がわからないこと。TOEFL頻出単語をまとめた単語帳を使い、毎日20語ずつ覚えるようにしました。ただし、単語だけを覚えるのではなく、文脈の中で覚えることを重視。例えば “abundant” という単語は、「水資源が豊富」などの例文とセットで覚えることで、記憶に定着しやすくなります。 - 構文の理解
長文読解では、文の構造を見抜く力が必要です。関係代名詞、分詞構文、倒置など、複雑な構文が頻出します。私は高校英文法の参考書を引っ張り出し、構文ごとに例文をノートにまとめて、何度も音読しました。音読は、構文のリズムを体で覚えるのに効果的です。 - 読む「量」をこなす
最終的に読解力を伸ばすには、やはり「量」が必要です。私はTOEFLの過去問だけでなく、英字新聞(New York TimesやBBC)、英語の教養書、大学の教科書なども読みました。最初は1ページ読むのに30分かかっていましたが、徐々にスピードが上がり、内容の理解も深まりました。
◇読解力は「ビジネス英語力」にも直結する
読解力を鍛えたことで、TOEFLのスコアが伸びただけでなく、私のこれまでの各業界での英語を使う仕事にも大きな影響を与えています。現在在籍している製薬業界でのマーケティング活動では、日々の業務の中で英語の論文や海外の調査レポートを読む機会が多くあります。以前は「読むのが苦痛」だったのが、今では「読むことで情報を得る楽しさ」に変わりました。
また、読解力がつくと、英語のプレゼン資料やメールの理解も速くなり、意思決定のスピードが上がるという副次的な効果もあります。
◇TOEFL読解の「コツ」:私が実践した5つの方法
TOEFLの読解セクションに特化して、私が実践した具体的なコツを紹介します:
- 設問を先に読む
文章を読む前に設問を確認することで、何を探すべきかが明確になります。特に「主旨」「語彙の意味」「文の挿入位置」などの設問は、先に意識しておくと効率的です。 - 段落ごとに要約する
読みながら、各段落の要点をメモするクセをつけました。これにより、文章全体の構造がつかみやすくなります。 - 知らない単語は文脈で推測する
TOEFLでは辞書は使えません。知らない単語が出てきたら、前後の文脈から意味を推測する練習をしました。これは、実際の試験でも非常に役立ちました。 - 時間を計って読む練習
TOEFLは時間との戦い。私はストップウォッチを使って、1パッセージ15分以内で読む練習を繰り返しました。 - 間違えた問題は「なぜ間違えたか」を分析する
正解・不正解だけでなく、「なぜその選択肢を選んだのか」「なぜ正解ではなかったのか」をノートに記録。これが、次回以降の正答率アップにつながりました。
◇読解力は「年齢に関係なく」伸ばせる
50代になってからの英語学習は、確かに若い頃よりも時間がかかります。でも、経験と集中力がある分、理解の深さはむしろ増していると感じます。読解力は、年齢に関係なく伸ばせる力。むしろ、人生経験があるからこそ、文章の背景や文脈を深く読み取れるのかもしれません。
~まとめ:読む力は、英語力の「土台」!~
TOEFLの読解セクションは、単なる試験対策ではなく、英語力そのものを底上げするチャンスです。単語力、構文理解、読む量——これらを意識して積み重ねることで、確実に「読む力」は伸びていきます。
そしてその力は、留学後の学術的な読解、ビジネスでの情報収集、さらには日常の英語コミュニケーションにもつながっていきます。
「読む力」は、英語力の土台。よく学生時に読んでいたのが、英語の横に和訳がついている
次回Vol.4では、TOEFLスピーキングで差をつける「表現力」について、私が実践したフレーズや練習法を紹介します。英語で「話す」ことに苦手意識がある方、ぜひご期待ください!
☆☆☆☆☆☆☆☆ 英語学習者向けの古典作品(和訳付き)☆☆☆☆☆☆☆☆
1. 『英語で読む シェイクスピア珠玉の15篇』
- 出版社:IBCパブリッシング
- 特徴:
- ラム姉弟によるシェイクスピアの簡易ノベライズを、さらに英語学習者向けにやさしくリライト。
- 『ハムレット』『マクベス』『オセロー』『リア王』など、代表的な15作品を収録。
- 英語+和訳の対訳形式、音声ダウンロード付き。
- ページ数:約440ページ(やや厚めですが、1話ずつ短く読める構成)
- Kindle購入リンク:Amazonで見る
2. IBC対訳ライブラリーシリーズ(他の古典も多数)
- 出版社:IBCパブリッシング
- シリーズ内容:
- シェイクスピア以外にも、オスカー・ワイルド、マーク・トウェイン、ジェーン・オースティンなどの古典作品を英語+和訳で収録。
- 各巻は比較的薄め(200〜300ページ程度)で、持ち運びにも便利。
- 英語学習者向けにリライトされており、辞書なしでも読みやすい。
- Kindle購入リンク:シリーズ一覧は IBCパブリッシング公式サイト や Amazon で「IBC対訳ライブラリー」と検索すると見つかります。
3. 『ラダーシリーズ』 by アイビーシー・パブリッシング(IBC)
- 出版社:IBCパブリッシング
- 特徴:
- 英語のみですが、語彙レベル別に構成されており、初心者〜中級者向け。
- シェイクスピアや他の古典も収録されている。
- 和訳はついていませんが、簡易英語で書かれているため、辞書なしでも読みやすい。
- Kindle購入リンク:Amazonで「ラダーシリーズ シェイクスピア」などで検索すると見つかります。
☆おすすめの選び方☆
- **対訳形式(英語+日本語)**を希望する場合は「IBC対訳ライブラリー」シリーズが最適。
- 英語のみでも簡易な文章で読みたい場合は「ラダーシリーズ」もおすすめ。
- Kindle対応のものは、Amazonで「Kindle版」表記があるかを確認してください。
~MEDIA50s語学・留学特集シリーズ予定~
- 名詞の不規則変化(Vol.1)
- 動詞の時制と不規則変化(Vol.2)
- TOEFL読解のコツ(今回)
- スピーキングで差をつける表現(次回)
- 留学後のキャリア形成と英語力
ご感想やご質問があれば、ぜひコメント欄へ。次回も一緒に学びましょう!